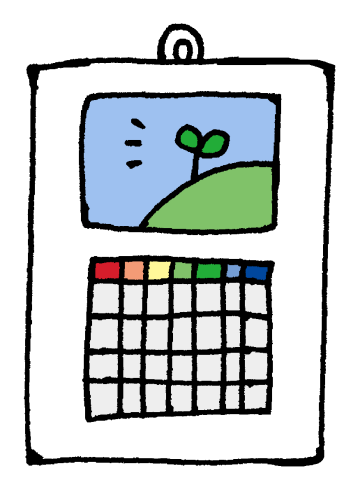墓誌
墓誌とは

故人の戒名(法名)、俗名、命日、年齢などを刻んだ石碑を墓誌といいます。
一般的には墓石の隣に建てられます。
お墓に納められた人々の身元やいつ亡くなったかを、後代に伝える役割を担っています。
「霊標」「墓標」「戒名板」「法名碑」などとも呼ばれます。
よくある質問
Q.墓誌は作った方がいいですか?
A.後から見た時に故人のことが明確に理解できるように、墓誌を建てることをお勧めしています。
名前、戒名、没年月日など、墓石に刻むのが理想的ですが、スペースに限りがあるため、通常は約8名分しか刻むことができません。
独立した石碑の墓誌を建てることで、亡くなった方の記録をより多く残すことができます。
墓石・墓誌に刻む名前の順番
墓誌に名前を彫刻する際、世代順に刻むことをご提案しています。
後にご子孫が墓誌を見た時に、先祖の関係性や順序が理解しやすいというメリットがあるためです。
具体的には、一代目の夫婦を刻んだ後、二代目の夫婦、そして三代目の夫婦といった順序で、夫婦単位で情報を刻みます。
まだ亡くなっていない人のところは空欄にして、次の人の情報を刻んでいきます。
たとえば、墓を継ぐ方の妻が先に亡くなった場合、その方(夫)のスペースを空けて、亡くなった妻の名前を刻むようにします。
子どもさんが両親よりも先に、若くして亡くなった場合、両親のスペースを空けて、子どもさんの俗名の部分に「〇〇(親の名前)の子△△(子の名前)」と刻むようにします。
※すべて施主様に確認を取ったうえで行います。
Q.墓石に戒名が刻まれている人は墓誌に刻字は必要ありませんか?
A.墓誌は「過去帳」でもあるため、墓石に戒名が刻まれている人でも、墓誌にも刻むことをお勧めしています。
墓石に戒名(法名)が刻まれている人は墓誌に刻まなくてもいいとおっしゃるご住職もおられます。
しかし、墓石に戒名があっても、墓誌に重複して刻むことに問題はありません。
墓誌は「過去帳」の役割も果たしており、むしろ墓誌にも戒名を彫る方が良いでしょう。
墓石には戒名しか刻まれていないことがあるため、誰のことかが分からないことがあります。
墓誌では戒名の下に俗名(=生前に使っていた本名)が刻まれているので、誰のことかわかります。
何世代かあとのご子孫が墓誌を見て、自分のルーツを知り、繋がれてきた命の尊さを感じます。
Q.墓誌に刻まれなかった先祖の情報を追記してもいいのでしょうか?
A.ぜひ追記してください。
昔は幼くして亡くなる子どもが多かったため、亡くなっても墓誌に何も刻まれないことはよくあったそうです。
しかし、そのことが気になり、後から名前などを墓誌に追記したいと考える方がいらっしゃいます。
全く問題ありませんので、是非そのようにしていただければと思います。
墓誌に名前を後から刻む際には、誰が誰の子であるかを明示することが大切です。
後の世代が家族のつながりを理解しやすくなります。
お墓の専門家、山口からみなさまへ
最近では、一つのお墓に複数の人が一緒に納められることがよくあります。
例えば、ご主人のお墓に奥様のご両親も一緒に納められることがあります。
このような場合、墓誌にきちんと記録を残すことが大切です。
なぜなら、墓誌に記載がないと、誰がお墓に納められているのかが分からず、「この人は誰?」という疑問が生じる可能性があるからです。
このような理由から、墓誌を建てることは昔以上に有益だと感じています。
墓誌に記載することで、誰がお墓に眠っているかが明確にわかり、将来の世代が過去の家族や先祖のつながりを理解しやすくなります。
墓誌は家族の歴史と絆を守る大切な手助けになりますよ。