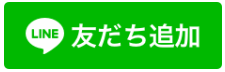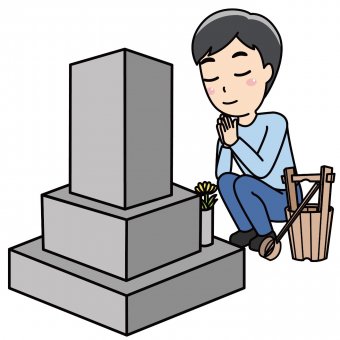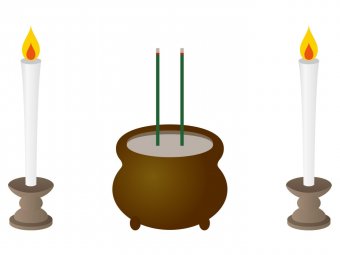お骨は骨壷から出すの?
よく墓石の中に骨壷のまま納める方がいらっしゃいますが、本来ならばお骨は土に帰っていただくのが自然の姿であります。
骨壷の中の状態では、土に帰ることも出来ませんし、下手をすると長年の結露や雨水で壷の中に水が溜まってしまっているケースもあります。
この状態で『ご先祖様、成仏してください!』とは変な話しだと思います。
地方によっては骨壷のまま納める風習の場所もありますので、それを否定するわけではありませんが、できる限りお骨が土に帰って頂けるような墓のつくりを石屋さんにしてもらってください。
間違っても草が生えるからなどと、墓石の中(底)をコンクリートで覆ってしまうとかは避けられた方がよいですね。
墓石はお骨を納める場所であり、 供養塔などはご先祖様を供養する為の碑であります。 間違っても記念碑などではありません。
コケが付いていて価値が上がるなどと考えずに 、いつも綺麗に掃除 をされ、ご先祖様を中心に考えられて行動をしてみてください。
命日などには墓参りに行くなど・・・。
そうすると物事が良い方向に進んでいきますし、先祖を大事にしてくれる子孫をご先祖様が助けてくれます!

LINEからのお問い合わせ・ご連絡も歓迎です。
まずはお友だち申請をお願いします。