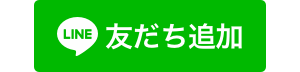納骨の仕方
 山口 博士
山口 博士
あまり必要のない情報ですが普段僕がしていることを。
お客様からのご依頼があった場合、弊社は納骨のお手伝いもさせて頂いております。
当日は事前にお墓のお掃除をさせて頂きキレイになった状態でお施主様(ご親族)を墓所にてお迎えさせて頂きます。
お墓用の小さなテーブルとフキン、ろうそく・線香セットを持参し準備しておきます。
ご住職(神職様)によって、先にお墓のお参りをされる方もいれば、納骨が先という場合もありますので、ご住職や神職様に確認をとってのお手伝い開始となります。
①和墓の場合は、まず花立て2つと香炉1つを正面から移動します。
移動しますと、お墓の正面に骨穴が出てきます。
そこにお骨を収めます。
特にこの中部地方は骨壺のままではなく、お骨だけお墓に納める風習です。
お骨が大地に戻っていかれるようにする意味です。
②次に骨壺の蓋をあけて、頭の骨を蓋の上に予め分けておきます。丸い形をしたものが頭蓋骨です。
頭の骨は一番最後に納めます。
理由は身体が逆さまにならないようにするため。
③その次に骨壺を包んであった白い化繊の風呂敷を骨穴の周りに敷き、お骨をこぼさないように広げておきます。
これで納骨の準備が完了。
④ご住職がお経をあげて頂いている間に、ご家族、ご親族が順番にお骨を少しずつ納めて頂きます。
火葬場から沢山お骨をもって来られたら、親族の皆さんにも納骨をしてもらった方がよいでしょう。
量が少なければ、ご遺族のみだけでも構いません。
皆さん終わりましたら、残りを喪主さんご遺族が全て納めます。
分骨をしないのであれば、喉仏などのお骨も全て納め、最後に頭蓋骨の骨を被せるように納めて終わりになります。
喉仏などが収まっていた小さな木箱やガラスの蓋なども納めません。
化繊の風呂敷も入れないようにします。
時々古い位牌などを納める方もいますが、お墓はお骨を収める場所なので、お骨以外を納めることはお勧めしません。
白木の位牌などは、住職にご相談して処分してもらってください。
最後に、こぼれたお骨が無いかを確認し花壺と香炉を元の位置に戻します。
これで納骨が終わりですが、
納骨が終わったあとにロウソク・線香に火を灯し、線香をお一人1本お墓にお供えします。
焼香の代わりですね。
以上が納骨法要の流れです。
*宗教、宗派によって流れが違いますので、都度ご住職や神職様(専従の方)にお聞きしながらのお手伝いになります。
納骨が終わってからは、皆さんで故人の思い出などを話して頂き、故人を偲んで頂けると故人も喜ばれます( ´艸`)
もし納骨でお手伝いが必要でしたら、ご連絡くださいね。
普段必要のない納骨の作法でしたが、このお仕事させて頂いていると頻繁にありますので、少し記してみました( ´∀` )
LINEからのお問い合わせ・ご連絡も歓迎です。
まずはお友だち申請をお願いします。



.png)
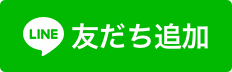
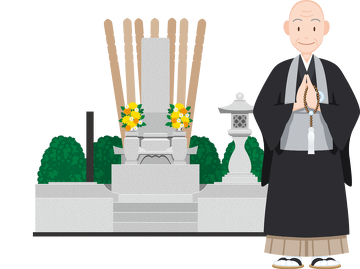


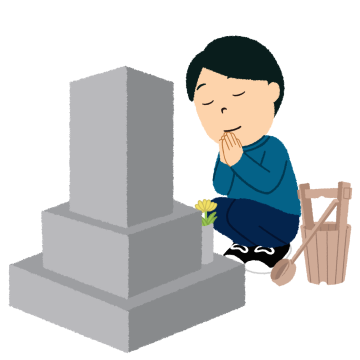
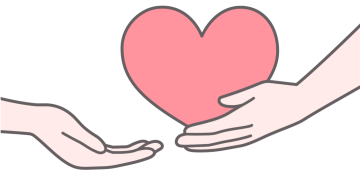
.png)

.png)